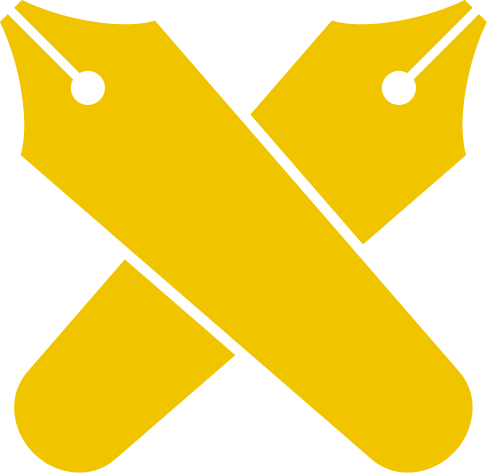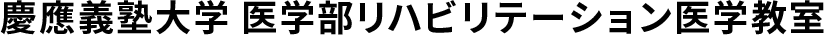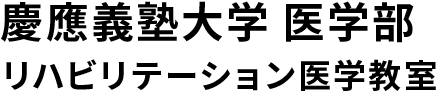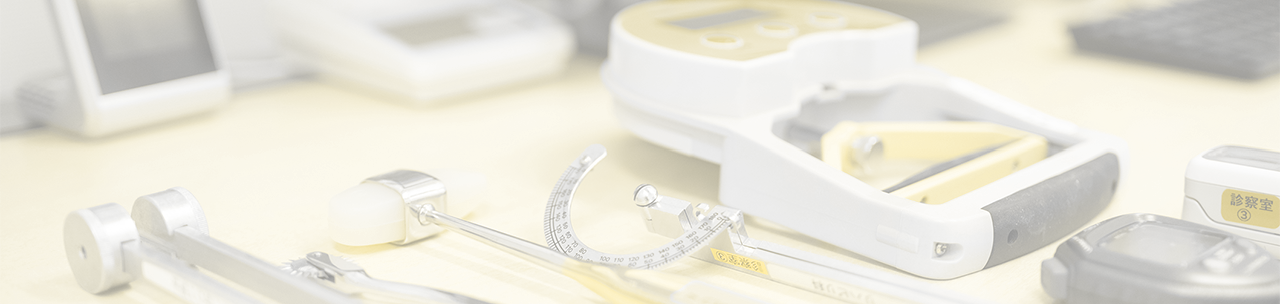業績紹介/受賞
当教室では、神経生理学や運動生理学、脳科学を治療に応用するニューロリハビリテーション、がん患者のADLやQOLを調え高めるがんリハビリテーション、再生医学や分子生物学にまつわる再生リハビリテーション、これまで見過ごされていた障害の側面を詳らかにする新しい評価法の開発、最先端の技術とリハの融合を目指すリハビリテーション工学・ロボットリハビリテーション、心疾患患者を対象とした緻密な心臓のリハビリテーション、地域医療や災害支援に関する地域リハビリテーションや災害リハビリテーション、各種疾患・障害に対する専門的リハビリテーション、リハビリビリテーション心理学など幅広いテーマに取り組んでいます。
上のボタンをクリックしますと、pubmedにて当教室の業績一覧がご覧になれます。
*定期的にチェックしておりますが、当教室に関係ない論文が検索されてくるようでしたらご一報くださいますようお願い申し上げます。
以下、主な研究成果です。タイトルをクリックするとアコーディオンが開き、邦語で概要を閲覧になれます。
最近の論文
Yamada Y, Kawakami M, Tashiro S, Omori M, Matsuura D, Abe R, Osada M, Tashima H, Shimomura T, Mori N, Wada A, Ishikawa A, Tsuji T. Rehabilitation in acute COVID-19 patients: A Japanese retrospective, observational, multi-institutional survey. Arch Phys Med Rehabil. 2021
関連病院の急性期病院でデータ取得したCOVID19のリハビリテーションに関する多施設研究で、未知の新たな感染症に対し、リハビリテーションがどのように行われていたかを示す貴重な研究となりました。
Tashiro S, Tsuji O, Shinozaki M, Shibata T, Yoshida T, Tomioka Y, Unai K, Kondo T, Itakura G, Kobayashi Y, Yasuda A, Nori S, Fujiyoshi K, Nagoshi N, Kawakami M, Uemura O, Yamada S, Tsuji T, Okano H, Nakamura M. Current progress of rehabilitative strategies in stem cell therapy for spinal cord injury: a review. NPJ Regen Med. 2021 Nov 25;6(1):81. doi: 10.1038/s41536-021-00191-7.
当教室では、整形外科学教室・生理学II教室との共同研究の中で再生リハビリテーションについて研究を進めています。再生リハビリテーションは再生医療に併用されるリハビリテーション手法のことで、移植された幹細胞の生着や神経分化、宿主神経回路への統合などに欠かすことのできない治療手段です。脊髄損傷に対する再生医療とリハビリテーションの併用について、基礎と臨床の両面から総覧し、明らかになっている機序や課題、展望について論じました。この分野の総説は非常に少なく、本邦からはおそらく初めてのものです。以下からopen accessでご覧頂けます。https://rdcu.be/cB1Ee
Iwasawa T, Fukui S, Kawakami M, Kawakami T, Kataoka M, Yuasa S, Fukuda K, Fujiwara T, Tsuji T. Factors related to instrumental activities of daily living in persons with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Chron Respir Dis. 2021 Jan-Dec;18:14799731211046634.
肺高血圧症の中でCTEPHは治療方法の確立に伴い、リハビリの重要性が認識され始めているが、この疾患のADL,IADLの特性についてはまだ知られておらず、それを明らかにした報告。オープンアクセスなので、無料でダウンロードできます。肺高血圧症を臨床で診る先生方はぜひご覧くださいませ。
Shibata T, Tashiro S, Shinozaki M, Hashimoto S, Matsumoto M, Nakamura M, Okano H, Nagoshi N.Treadmill training based on the overload principle promotes locomotor recovery in a mouse model of chronic spinal cord injury.Exp Neurol. 2021 Aug 8;345:113834. doi: 10.1016/j.expneurol.2021.113834. Online ahead of print. PMID: 34370998
これまで脊髄損傷モデル動物の四足歩行訓練には統一されたプロトコルはなく、適切な訓練強度や訓練時間は不明でした。過負荷の原理に沿ったプロトコルを作成し、慢性期脊損マウスの歩行訓練を行ったところ、走行距離との間に相関を持った機能回復を認めました。適切な訓練時間、必要な馴化期間等についても合わせて検討しました。さらに神経栄養因子発現増加などの分子的変化も合わせて報告しました。こちらは先日の運動療法学会にて最優秀演題賞を受賞した内容になります。
Keita Tsuzuki , Michiyuki Kawakami , Takuya Nakamura, Osamu Oshima, Nanako Hijikata , Mabu Suda, Yuka Yamada, Kohei Okuyama and Tetsuya Tsuji .Do somatosensory deficits predict efficacy of neurorehabilitation using neuromuscular electrical stimulation for moderate to severe motor paralysis of the upper limb in chronic stroke? Ther Adv Neurol Disord 2021, Vol. 14: 1–11 DOI: 10.1177/17562864211039335
慢性期脳卒中患者に対して行ったIVESを用いた上肢リハ(HANDS療法)の良好な改善を予測する因子として、介入前の運動機能だけでなく感覚障害の程度が抽出された。都築先生の学位論文で、感覚障害が運動機能改善に関係するのか?という普遍的なquestionに一つの答えを提示した論文です。
Takeuchi S, Uemura O, Unai K, Liu M., Adaptation and validation of the Japanese version of the Spinal Cord Independence Measure (SCIM III) self-report. Spinal Cord 2021. https://doi.org/10.1038/s41393-021-00633-5
脊髄損傷患者の日常生活自立度(ADL)を評価するために、脊髄障害自立度評価法(SCIM-III)が広く利用されています。SCIM-IIIは3領域(セルフケア、呼吸・排泄、移動)にわたる19項目、100点満点で、入院患者を医療従事者が観察することで評価する方法です。SCIM-IIIはイスラエルで開発され、日本語版は国立病院機構村山医療センターと当教室で作成し、その信頼性と妥当性を学術誌で報告しました。一般的に用いられるFIMよりも脊髄損傷特異的な領域(呼吸や排尿など)について、より詳細に評価することが出来るため、脊髄損傷患者のADL評価法として世界標準となっています。
一方でSCIM-IIIは観察により評価する性質上、外来患者のADL評価には向きません。事実、多くの患者が長期にわたって過ごすはずの退院後のADL評価報告は少なく、日常診療でも定量的な評価は行われてきませんでした。そこで、これらの問題を解決すべく自己採点方式の評価法であるSpinal Cord Independence Measure – self report (SCIM-SR)がスイスで開発されました。SCIM-IIIと同様の19項目、100点満点の評価法です。
今回、我々はSCIM-SRを日本語に翻訳し、SCIM-IIIとの妥当性を検証し学術誌に報告しました。脊髄の再生医療が現実となりつつある現在、外来の脊髄損傷患者のADL評価は欠かせないものになると予想されます。そのためには入院時のADL評価と相同な評価法が必須となるため、SCIM-SRはその中心的役割を担うことが期待されます。
Haruyama K. Kawakami M. Okada K. Okuyama K. Tsuzuki K. Liu M.
Pelvis-Toe Distance: 3-Dimensional Gait Characteristics of Functional Limb Shortening in Hemiparetic Stroke.
Sensors 2021, 21, 5417. https://doi.org/10.3390/s21165417
下肢に新たに定義した距離が,健常対照者と比較して片麻痺歩行の特徴を捉えられるかどうかを調べることを目的とした.慢性脳卒中患者42名と、年齢をマッチさせた対照者10名を対象に、三次元歩行解析を行った。骨盤-つま先間距離(PTD)は、歩行中の前上腸骨棘マーカーと足指マーカー間の絶対距離を両脚支持期のPTDで正規化して算出した。また,遊脚期の短縮ピークをPTDminとして定量化した。脳卒中群のPTDminは、対照群と比較して、患側では短縮が少なく、非患側では過剰に短縮していた。脳卒中患者のPTDminは、歩行速度および観察的歩行スケールと中程度から高い相関を示した。PTDminは、前額部の代償パターンによる見かけ上の改善に影響されることなく、歩行の質を適切に反映していた。
Hiroki Okawara, Syoichi Tashiro, Tomonori Sawada, Keiko Sugai, Kohei Matsubayashi, Michiyuki Kawakami, Satoshi Nori, Osahiko Tsuji, Narihito Nagoshi, Morio Matsumoto, Masaya Nakamura. Neurorehabilitation using a voluntary driven exoskeletal robot improves trunk function in patients with chronic spinal cord injury: a single-arm study. Neural Regeneration Research, 17, 2. 427-432 DOI:10.4103/1673-5374.317983
2016-2018にかけて慶應病院でHALを用いた慢性期脊損の臨床研究を行っており、このたびChinese Association of Rehabilitation Medicine 主催のNeural Regeneration Medicine誌 IF5.135 よりpublishされました。慢性期であってもRobot-assisted Gait trainingを行うことで体幹筋力が増加することを明らかにしました。筆頭の大川原洋樹先生は整形外科所属の理学療法士として活躍されている方です。
Nagumo, M., Tashiro, S., Hijikata, N., Ishikawa, A., Akiyama, T., & Tsuji, T. (2021). Conservative rehabilitation for a patient presenting with severe orthostatic hypotension after surgical management of brainstem tumor: illustrative case, Journal of Neurosurgery: Case Lessons, 1(25), CASE2136. Retrieved Jul 29, 2021
脳幹部腫瘍術後血圧調節障害が遷延し、リハに難渋した症例に対する詳細なアプローチをわかりやすいシェーマとともにまとめ、今回accept, publishに至りました。脳神経外科領域におけるリハビリテーションの報告は当科領域の啓発という観点からも意義深いと考えております。
Hasegawa T, Akechi T, Osaga S, Tsuji T, Okuyama T, Sakurai H, Masukawa K, Morita T, Kizawa Y, Tsuneto S, Shima Y, Miyashita M. Unmet need for palliative rehabilitation in inpatient hospices/palliative care units: a nationwide post-bereavement survey. Jpn J Clin Oncol. 2021 Jun 11:hyab093. doi: 10.1093/jjco/hyab093.
ホスピス財団が継続的に実施している「遺族によるホスピス・緩和ケアの質の評価に関する研究(J-HOPE)」の一環として、ホスピス・緩和ケア病棟におけるリハビリテーション治療の必要性を検討しました。
Fukushima T, Tsuji T, Watanabe N, Sakurai T, Matsuoka A, Kojima K, Yahiro S, Oki M, Okita Y, Yokota S, Nakano J, Sugihara S, Sato H, Kawakami J, Kagaya H, Tanuma A, Sekine R, Mori K, Zenda S, Kawai A. The current status of inpatient cancer rehabilitation provided by designated cancer hospitals in Japan. Jpn J Clin Oncol. 2021 May 15:hyab070. doi: 10.1093/jjco/hyab070.
全国のがん診療連携拠点病院対象にしたアンケート調査です。入院中のがん患者に対するリハビリテーション治療の実施状況を分析し、入院中にはほぼ全施設でリハビリテーション治療が実施されていたものの不十分と感じる施設は多く、その理由としてマンパワー、知識・技術の習得が要因としてあげられたというものです。
Abe K, Tsuji T, Oka A, Shoji J, Kamisako M, Hohri H, Ishikawa A, Liu M.Postural differences in the immediate effects of active exercise with compression therapy on lower limb lymphedema. Support Care Cancer. 2021 Apr 29. doi: 10.1007/s00520-020-05976-y.
下肢続発性リンパ浮腫患者を対象に、多層包帯法による圧迫下での運動(エルゴ)の即時的な浮腫改善効果の姿勢による違いを明らかにしたRCTです。臥位での運動のほうが座位での運動よりも効果が高いことがわかりました。
Fukui S, Kawakami M , Hayashida K, Ishikawa A, Mori N, Oguma Y, Fukuda K, Tsuji T. (2021) Functional Status and Instrumental Activities of Daily Living after Transcatheter Aortic Valve Replacement. Top in Geriat Rehabil. 2021; 37 (2): 128-131.
高齢重度の大動脈弁狭窄症患者において、TAVI治療後6か月でIADLや栄養状態が改善していました。
Nakamura T, Kawakami M, Fukui S, Takeuchi S, Liu F, Kawaguchi S, Hayashida K, Shimizu H, Fukuda K, Tsuji T, Liu M. Incidence and risk factors of postoperative dysphagia in severe aortic stenosis. Top in Geriat Rehabil. 2021; 37(2): 58-63.
大動脈弁狭窄症患者において、TAVIと外科的弁置換術で術後の嚥下障害の発生率を比較した、外科的手術は一過性の嚥下障害を呈する割合が多いが、長期的には嚥下障害が残存するリスクはどちらの介入でも低かったことを報告しました。
Nishida D, Mizuno K, Yamada E, Liu M, Hanakawa T, Tsuji T. Correlation between the brain activity with gait imagery and gait performance in adults with Parkinson’s disease: A data set. Data in Brief 2021;36 doi: 10.1016/j.dib.2021.106993
パーキンソン病患者さんの歩行障害は日常活動を低下させますが、リズム刺激で改善することがわかっていますが、そのメカニズムはわかっていません。そこで機能的核磁気共鳴画像法(fMRI)を用いて、歩行時の脳内メカニズム解明に挑みました。結果、パーキンソン病患者は歩行イメージ時に左弁蓋部が過活動になり、音リズム刺激でその過活動が抑制されることを示しました。この結果から弁蓋部は感覚と運動をつなぐ部位と考えられており、その機能不全があるパーキンソン病患者で歩行時に負荷がかかっており、それを音リズム刺激が負荷を緩和し、機能を補うのではないかと考えられます。
Mizuno, K.; Tsujimoto, K.;Tsuji, T. Effect of Prism Adaptation Therapy on the Activities of Daily Living and Awareness for Spatial Neglect: A Secondary Analysis of the Randomized, Controlled Trial. Brain Sci. 2021, 11, 347. https://doi.org/10.3390/brainsci11030347.
過去に行った半側空間無視に対するプリズム適応療法のRCTの2次解析で、プリズム適応群はADL上の半側空間無視症状の評価であるCBSの項目の中で、視線、所有物の探索、の2項目に特に改善が見られました。また、自身の無視症状に対する認識を示す病態失認スコアの絶対値が、プリズム群ではコントロール群より治療後早期に改善が認められ、最終的にも有意に改善していたということが示されました。元になったRCTの論文ではプリズム適応療法後にリハビリテーション治療を継続することによってFIM gainが有意に改善することが示されましたが、今回の解析で無視に対する自己認識が先行して改善することにより、リハビリテーション治療の効果を高める可能性が示唆されました。
Tashiro S, Kuroki M, Okuyama K, Oshima O, Ogura M, Hijikata N, Nakamura T, Oka A, Kawakami M, Tsuji T, Liu M. (2021) Factors related to daily use of the paretic upper limb in patients with chronic hemiparetic stroke—A retrospective cross-sectional study. PLoS ONE 16(3): e0247998.
慢性期脳卒中患者において、麻痺手の使用頻度を規定する因子の検討です。運動機能に加えて、感覚機能(触覚)が麻痺手の使用頻度に関連していました。
Suda M, Kawakami M , Okuyama K, Ishii R, Oshima O, Hijikata N, Nakamura T, Oka A, Kondo K, Liu M. Validity and Reliability of the Semmes-Weinstein Monofilament Test and the Thumb Localizing Test in Patients with Stroke. Front Neurol. 2021
脳卒中患者における感覚評価は意外と信頼性、妥当性が証明された手法が少なく、今回は、表在覚の評価としてSWMT, 深部覚の評価として母指探し試験の信頼性と妥当性を報告しました。これらの評価をスクリーニングとして使用することの裏付けです。
Nakayama H, Kawakami M, Takahashi Y, Kondo K, Shimizu E. The changes in spinal reciprocal inhibition during motor imagery in lower extremity. Neurol Sci. 2021
足関節の背屈イメージ、底屈イメージが相反性抑制に与える影響を検証した論文です。非練習下においては底屈イメージが相反性抑制を修飾したのに対し、背屈イメージは有意な変化を認めませんでした。が、背屈の運動イメージを練習した後では相反性抑制を修飾しました。足関節において背屈運動イメージは難易度が高い可能性と、練習によってそれが強化できる可能性が示唆されています。
Shuhei Mayanagi, Aiko Ishikawa, Kazuaki Matsui, Satoru Matsuda, Tomoyuki Irino, Rieko Nakamura, Kazumasa Fukuda, Norihito Wada, Hirofumi Kawakubo, Nanako Hijikata, Makiko Ando, Tetsuya Tsuji, Yuko Kitagawa. Association of preoperative sarcopenia with postoperative dysphagia in patients with thoracic esophageal cancer, Diseases of the Esophagus, doaa121,
食道癌のサルコペニアを研究されていた一般消化器外科の先生とのコラボで、周術期のリハ評価や訓練など嚥下関係の部分をこちらで執筆したものです。
Syoichi Tashiro,Naoki Gotou,Yuki Oku,Takahiro Sugano,Takuya Nakamura,Hiromi Suzuki,Nao Otomo,Shin Yamada,Tetsuya Tsuji,Yutaka Asato andNorihisa Ishii
Relationship between Plantar Pressure and Sensory Disturbance in Patients with Hansen’s Disease—Preliminary Research and Review of the Literature Sensors 2020, 20(23), 6976; https://doi.org/10.3390/s20236976
【要旨】ハンセン病患者の足底知覚と歩行時足底圧分布の関係をうまく示した研究はありませんでしたが、臨床グレードごとに分けた場合に、中等度症例(グレードII:足部の変形は無いが、足底潰瘍があるかそれに繋がりうる創や胼胝形成を繰り返している症例)では知覚が保たれている部位に荷重する傾向があることを文献まとめとともに報告しました。障害像を基本的ですが重症度で分けるという姿勢を初めて導入した点と、ハンセン病研究を整理した学術的価値が認められました。
Hijikata, N., Kawakami, M., Wada, A., Ikezawa, M., Kaji, K., Chiba, Y., Ito, M., Fujino, E., Otsuka, T., & Liu, M. (Accepted/In press). Assessment of dysarthria with Frenchay dysarthria assessment (FDA-2) in patients with Duchenne muscular dystrophy. Disability and Rehabilitation. https://doi.org/10.1080/09638288.2020.1800108
【要旨】FDA-2(構音障害の評価ツール)日本語版を作成し、信頼性・妥当性を検討し、それを用いてデュシェンヌ型筋ジストロフィーにおける構音障害を評価したという内容でございます。
Masato Kikuuchi, Yoshiteru Akezaki, Eiji Nakata, Natsumi Yamashita, Ritsuko Tominaga, Hideaki Kurokawa, Makiko Hamada, Kenjiro Aogi, Shozo Ohsumi, Tetsuya Tsuji and Shinsuke Sugihara. Risk factors of impairment of shoulder function after axillary dissection for breast cancer. Supportive Care in Cancer. 2020 March. https://doi.org/10.1007/s00520-020-05533-7
【要旨】乳がん術後の肩挙上障害に関わる因子の検討
Noriko Nakayama, Tetsuya Tsuji, Makoto Aoyama, Takafumi Fujino and Meigen Liu. Quality of life and the prevalence of urinary incontinence after surgical treatment for gynecologic cancer: a questionnaire survey. BMC Women’s Health (2020) 20:148
【要旨】婦人科がん術後の排尿障害のパターンと出現頻度のアンケート調査
Yoshida T, Mizuno K, Miyamoto A, Kondo K, Liu M. Influence of right versus left unilateral spatial neglect on the functional recovery after rehabilitation in sub-acute stroke patients. Neuropsychol Rehabil. 2020 Jul 23:1-22. doi: 10.1080/09602011.2020.1798255. Epub ahead of print. PMID: 32703088.
【要旨】湾岸リハのデータベースを利用した研究です。半側空間無視がリハビリテーションアウトカムに影響することはよく知られていますが、左半球損傷による右半側空間無視については、見過ごされていることが多いのが現状です。この論文では、右無視は左無視よりやや少ないですが、左半球損傷の30%程度で発生し、左無視と同じくADLのアウトカムを増悪させることを示しました。
受賞
最近の慶應義塾大学リハビリテーション医学教室・教室員の受賞は以下になります。
2023年11月 本教室の和田彩子専任講師、第27回日本遠隔医療学会学術大会において優秀論文賞を受賞!
令和5年11月11日-12日に朱鷺メッセ(新潟)で開催された第27回日本遠隔医療学会学術大会において、リハビリテーション医学教室の和田彩子専任講師が優秀論文賞を受賞した。
| 学会名: | 第27回日本遠隔医療学会学術大会 |
| 演題名: | 仮想避難所における同時多数人の活動量モニタリングのfeasibility study |
| 演者名: | 和田彩子・川上途行 |
| 賞名: | 優秀論文賞 |
| 概要: | 大規模自然災害等による集団避難生活が長期化すると生活不活発病を集団発生するリスクがある。仮想避難所生活環境下においてテレメトリー式生体信号測定装置を用い、同時に複数人の活動量を把握する検証を行い、一定空間内の同時複数人の活動量をリアルタイムで測定することが確認できた。活動量の集団モニタリングは避難所における生活不活発病のリスクを早期発見・早期介入するためのスクリーニングツールになり得る可能性が示唆された。 |
2023年11月 本教室の川畑有紗医師、第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会においてYoung Investigator Award(YIA)最優秀賞を受賞!
令和5年11月3日から5日に宮崎県シーガイアコンベンションセンターで開催された第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会において、当教室の川畑有紗医師がYoung Investigator Award(YIA)最優秀賞を受賞した。
本賞は40歳以下の若手研究者を対象にリハビリテーション医学・医療における学術研究の育成と症例のために設立された賞であり、事前審査と当日の口述発表により10名の候補者から受賞者が選ばれた。
| 学会名: | 第7回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会 |
| 演題名: | 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症患者の失調性構音障害におけるFDA-2を用いた検討 |
| 演者名: | 川畑有紗(独立行政法人国立病院機構東埼玉病院 リハビリテーション科) |
| 共同演者: | 和田彩子、渡邊瑠美、梶兼太郎、大塚友吉、川上途行、辻哲也 |
| 賞名: | Young Investigator Award(YIA) 最優秀賞 |
| 概要: | 脊髄小脳変性症・多系統萎縮症は失調を呈する神経変性疾患であり、その一症状である構音障害は患者・家族の生活に大きな影響を与える。本研究では脊髄小脳変性症・多系統萎縮症の構音障害についてFrenchay Dysarthria Assessment-2(FDA-2)を用いてその特徴を明らかにし、また臨床経過や一部の発声発語器官機能と相関がある可能性を示唆した。 |
2022年12月 山田祐歌助教、第52回日本臨床神経生理学会学術大会にて優秀演題賞受賞
令和4年11月24、25、26日に国立京都国際会館で開催された第52回日本臨床神経生理学会学術大会において、リハビリテーション医学教室の山田祐歌助教が優秀演題賞を受賞した。神経内科、脳神経外科、精神科、リハビリテーション科等が参加する学際的な同学会において発表演題5題に与えられる賞で、全329演題から選ばれた。受賞演題は「慢性期脳卒中片麻痺患者における電気刺激と健側上肢の使用制限の併用療法の効果 〜忍容性試験〜」である。本研究では、運動機能回復と同時に麻痺手の使用習慣化を促すための取り組みを実施し、高い忍容性と麻痺機能の改善効果を明らかにした。麻痺手の実用手獲得には、特に慢性期患者では困難とされている麻痺機能回復に加え、今まで使用してこなかった麻痺手を使用するという「行動変容」へのアプローチが重要であり、本報告ではその両者に着目した取り組み結果が評価された。
慢性期脳卒中片麻痺患者における電気刺激と健側上肢の使用制限の併用療法の効果 〜忍容性試験〜
山田祐歌、川上途行、紙本貴之、辻哲也
2022年12月 川上途行准教授、日本臨床神経生理学会第12回奨励賞受賞
本教室の川上途行准教授が日本臨床神経生理学会第12回奨励賞し、2022年11月24日から26日に開催された第52回日本臨床神経生理学会学術集会(京都)で受賞講演を行った。これは公募申請時に45歳以下で、臨床神経生理学分野で顕著な業績があり、将来のさらなる発展が期待される会員に送られる賞である
川上医師はこれまで脳科学、神経生理学に基づくニューロリハビリテーション手法の開発に従事し、経頭蓋磁気刺激によるMEP, SICIの評価、H波を用いた相反性抑制評価、SEPといった神経生理手法を用い、主に脳卒中患者を対象に病後の運動麻痺や痙縮、感覚障害の基礎的メカニズム、改善のメカニズムを研究してきた(Ther Adv Chronic Dis. 2019、Clin Neurophysiol. 2022、ほか)。研究結果を踏まえた上で、これまで治療が困難とされてきた脳卒中慢性期まで残存した重度運動麻痺に対し、脳波技術、運動イメージ、電気刺激、ロボティクスなどを用いた多くの新たな治療介入の効果を検証してきた(Ther Adv Neurol Disord. 2018、Disabil Rehabil. 2021、ほか)。これらが評価され今回の受賞となった。
当教室からは藤原俊之先生(当時慶應義塾大学講師、現順天堂大学教授)以来、二人目の受賞となった。
2021年9月 田代祥一非常勤講師第10回杏林医学会研究奨励賞受賞
田代祥一非常勤講師(杏林講師)が、研究論文”Probing EEG activity in the targeted cortex after focal transcranial electrical stimulation” Tashiro S, et al., Brain stimulation. 2020.13(3):815-818にて第10回杏林医学会研究奨励賞を見事受賞しました。
非侵襲的に脳機能を修飾できる経頭蓋電流刺激法は,簡便かつ安全にリハビリテーションの効果を増強させられる併用療法として大きな期待を集めています.時間分解能に優れる脳波で計測されるBrain stateは効果指標として重要ですが,電流刺激電極と脳波記録電極は別物であるため,刺激電極で覆われた部位,すなわち標的領野由来の脳波を記録する手段が乏しく,直接的な神経生理作用の検証が困難でした.田代君は刺激電極の中央に脳波電極を埋め込むという簡潔明快な手法を発明し,このハイブリッド電極により十分に脳波測定が可能であることを検証,報告しました.本手法は,従来必須と考えられてきた脳磁図や機能的核磁気共鳴の併用といった大掛かりな設備が不要で,多くの研究室で簡便に実施可能であるため,臨床神経生理学や神経リハビリテーション領域の研究・臨床を大いに振興する画期的な業績であると言える点が評価されました.
2021年8月 令和三年第46回運動療法学会最優秀演題
第46回運動療法学会におきまして、5S7脊髄再生研究室にて田代祥一非常勤講師が主に指導した、整形外科大学院D3の柴田 峻宏先生の報告が、最優秀演題に選出されましたのでご報告致します。
慢性期脊髄損傷モデルマウスに対する漸増負荷法トレッドミル訓練の有効性の検討
柴田 峻宏1,2),田代 祥一3, 4),名越 慈人1) ,岡野 栄之2),中村 雅也1)
これまで脊髄損傷モデル動物の四足歩行訓練には統一されたプロトコルはなく、適切な訓練強度や訓練時間は不明でした。今回、過負荷の原理に沿ったプロトコルを作成し、慢性期脊損マウスの歩行訓練を行い、走行距離との間に相関を持った機能回復が観察されました。また走行スピード等にも着目し、適切な訓練時間、必要な馴化期間等についても検討しました。基礎研究領域の運動療法の発展に寄与する研究であることが評価され、最優秀演題に選出されました。
所属
1) 慶應義塾大学医学部整形外科学教室
2) 慶應義塾大学医学部生理学教室
3) 慶應義塾大学医学部リハビリテーション医学教室
4) 杏林大学医学部リハビリテーション医学教室
2020年8月 田代祥一非常勤講師 Stroke2020 学会賞優秀口演賞 臨床研究部門受賞
第45回日本脳卒中学会学術集会にて学会賞優秀口演賞 臨床研究部門受賞
令和2年8月24、25日にWeb開催されたStroke 2020において、田代祥一非常勤講師が学会賞優秀口演賞 臨床研究部門を受賞した。脳神経外科、神経内科、脳卒中科、リハ科等が参加する学際的な同学会において臨床1題、基礎1題に与えられる賞で、誰もが経験の乏しい事前録画方式の発表のなか全2383演題の頂点に輝いた。受賞演題は「慢性期脳卒中患者におけるClosed-loop神経筋電気刺激を利用したニューロリハによる体性感覚皮質可塑性の誘導」である。本研究では、運動機能回復を目的としたニューロリハが感覚皮質可塑性を伴って深部覚回復を促すことを電気生理学的に初めて明らかにした。慢性期脳卒中では運動機能回復は得られづらく、感覚機能に着目した治療応用も視野に入る業績となる。ただ最も特筆すべきは介入・評価ともに多くの施設で実施可能な手法を用いている点にこそあると言える。閉ループ系の末梢電気刺激を応用した先進的ニューロリハを用いてはいるが、市販機材もあり比較的普及している。評価に用いた体性感覚誘発電位も、中規模以上の病院であれば十分実施可能だ。近年ニューロリハは介入評価共に複雑化・大掛かり化が顕著であり、脳磁図や機能的MRI、反復磁気刺激等の設備が必須であるかのような先入観が蔓延し、一般医療機関での研究意欲を縮退させている。「普通の手法」による卓越した報告は、広く研究意欲を刺激し、脳卒中研究の裾野を拡大させる点で高く評価されたと言えよう。